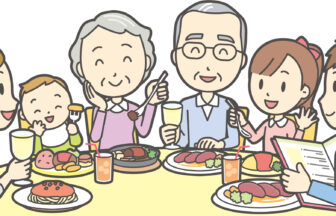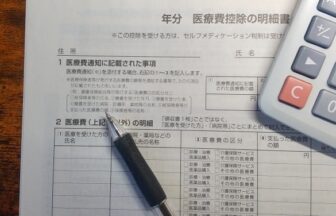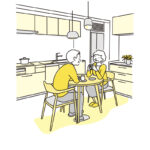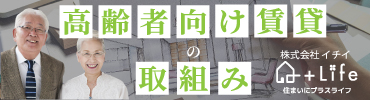親を扶養に入れることで、税金の軽減・社会保険の負担軽減などのメリットがあります。
しかし、親を扶養に入れるためには、所得制限・生計要件など、いくつかの条件を満たさなくてはなりません。
本記事では、親を扶養に入れる条件や控除額、手続きの流れを、具体例を交えながら解説します。
親を扶養に入れると何が変わる?メリットは?

親を扶養に入れると、以下3つのメリットがあります。
→扶養控除を適用し、所得税・住民税の課税対象となる所得を減らすことができる
メリット②社会保険料の軽減
→親が健康保険の扶養に入ると、健康保険料を支払う必要がなくなる
メリット③相続税対策
→親と生計を一緒にしていると、相続税の非課税枠が広がる場合がある
扶養控除が適用されると、所得税・住民税の負担が軽減されるだけでなく、保険料や相続税対策にもつながります。
まずは、親を扶養に入れるための条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
親を扶養に入れるための条件

親を扶養に入れるためには、生計・所得に関する条件を満たす必要があります。
条件を満たさない場合、税制上の扶養控除を受けられない・社会保険の扶養に入れないため、しっかり確認しておきましょう。
親を扶養に入れる条件1. 生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、同居はもちろん別居していても、生活費・療養費などを定期的に仕送りしている場合も含まれます。
たとえば、離れて暮らす親に毎月5万円を送金しているケース。
ほかにも、以下だと「生計を一にしている」とみなされ、扶養対象となる可能性があります。
【生計を一にしているとみなされる例】
・親と同居していて、同じ家計で生活している
・別居しているものの、毎月の生活費・医療費を仕送りしている
・親は老人ホームで生活中、老人ホーム入居費用を負担している
送金の証拠として、銀行の振込記録を残しておくと、税務調査が入った際に証明しやすくなります。
親を扶養に入れる条件2. 親の年間所得が48万円以下であること
親を扶養に入れるためには、親の年間所得が48万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)であることが条件です。
親が年金を受給している場合は、年金収入が65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下である必要があります。
・65歳未満の親:年金収入108万円(年間所得額48万円)→扶養に入れる
・65歳以上の親:年金収入160万円(年間所得額50万円)→扶養に入れない
(上記の年間所得額は、年金収入から年金の所得控除を差し引いた額です)※「年金の所得控除」について
・65歳未満は60万円(公的年金などの収入が年間130万円未満の場合)
・65歳以上は110万円(公的年金などの収入が年間330万円未満の場合)
また、親がパート収入を得ている場合も、年収が103万円以下なら扶養に入れます。
年末調整・確定申告の際、親の収入を確認しておきましょう。
親を扶養に入れるための条件は、国税庁の扶養控除ページにてご自身でもご確認ください。
あわせて、親を扶養に入れられるかどうか、お住まいのエリアの税務署へ確認することをおすすめします。
扶養控除の控除額
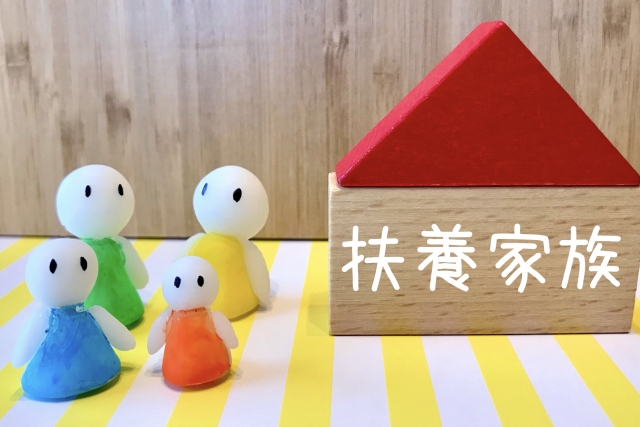
親を扶養に入れた場合の、所得税・住民税の控除額をみていきましょう。
控除額は、親の年齢・同居しているかどうかで異なります。
1. 所得税の控除額
所得税の控除額について、たとえば年収500万円の会社員が70歳以上の親を扶養に入れると、最大58万円の所得控除が受けられます。
親が70歳以上で同居・別居の場合の控除額と、70歳未満の親の場合の控除額は以下です。
・70歳以上の親(同居):控除額58万円
・70歳以上の親(別居):控除額48万円
・70歳未満の親:控除額38万円
控除額は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合に適用されます。
所得金額が900万円を超えると、控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると適用されません。
参考:国税庁「No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除」
2. 住民税の控除額
住民税の控除額についても、親の年齢や同居・別居により変わります。
・70歳以上の親(同居):控除額45万円
・70歳以上の親(別居):控除額38万円
・70歳未満の親:控除額33万円
住民税の場合、70歳未満の親を扶養に入れると控除額は33万円。
親が70歳以上だと、別居であっても控除額38万円、同居だと控除額が45万円になります。
なお、住民税の税率は10%です。
控除額の10%が住民税から減額されます。(例:控除額38万円だと38,000円の住民税減額)
親を扶養に入れる手続き(会社員・自営業やフリーランスの場合)

扶養控除を適用するためには、勤務先の年末調整や確定申告で申請が必要です。
会社員の場合、自営業やフリーランスの場合の方法をみていきましょう。
1. 会社員の場合:年末調整で申告
勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
申請が漏れると控除が受けられなくなるため、年末調整の際に忘れずに確認しましょう。
「扶養控除等(異動)申告書」は、下記の国税庁公式サイトからダウンロードできます。
参考:国税庁「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
2. 自営業・フリーランスの場合:確定申告で申告
確定申告書の扶養控除の欄に、親の情報を記入します。
親の所得証明書などを添付する場合もあるため、必要書類を確認しておきましょう。
親を扶養に入れるかどうか、まずは条件を確認してみよう

親を扶養に入れることで、所得税・住民税の控除を受けられるなどのメリットがあります。
ただ、所得要件や生計要件などを満たす必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。
詳細・最新情報は、国税庁のページにて確認できます。
親の扶養について迷った場合は、税務署や社会保険事務所に相談するのもひとつの手段です。
しっかりと準備を重ね、扶養控除のメリットを最大限活用しましょう。
おとなの住む旅では、アクティブシニア向け物件を中心に、住まいのご案内をしております。
家探しでお悩みの方は、家賃・条件・エリアとともにお気軽にお問い合わせください。

2024年末に閣議決定され、2025年に3万円給付はじめ、子ども手当・電気ガス代補助が予定されています。 ただ、対象となる世帯・申請方法と受給時期などは、お住まいの自治体の発表を確認する必要があります。 2025年1月現在、給付内容の詳細を発表している自治体を例にみていきましょう。 ...

医療費控除とは、年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が還付される制度です。 2024年分の医療費控除の申請スタートは、2025年2月17日(月)~。 本記事では、医療費控除の基本・申請方法について、注意点とあわせて解説します。 医療費控除とは? 医療費...